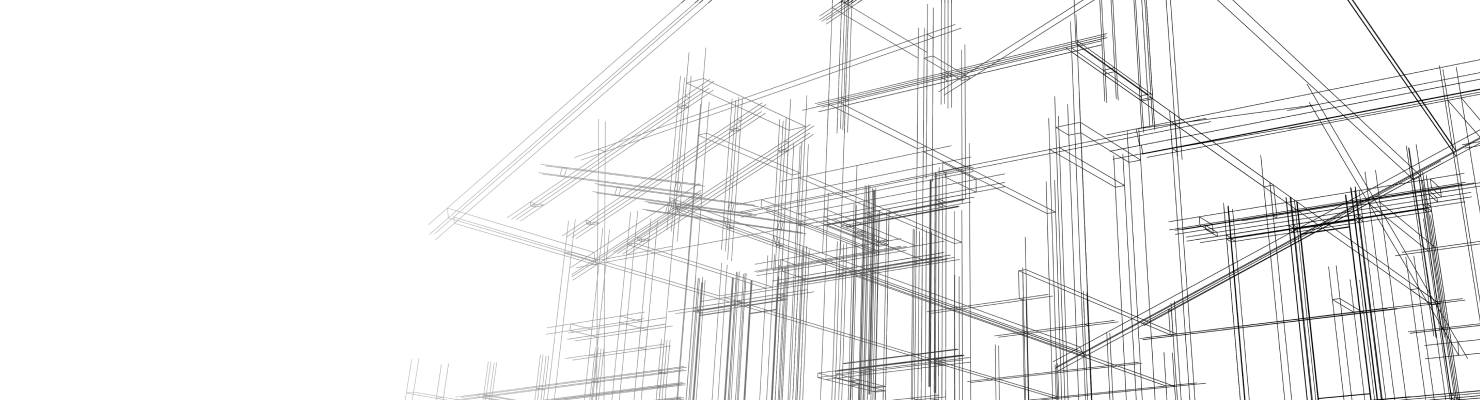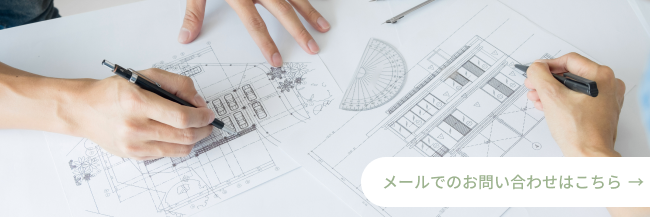土地探しのコツ
住まいの建替えは何度でも出来ます。でも、土地は一度決めたら簡単には動けません。 設計において、ある面カバーすることも出来ますが、土地選びは「家づくりの成功」を大きく左右する重大要素です。 ですから、さまざまな角度から念入りに調べることが必要なのです。

土地探しの必須条件
- 権利や法的規制はクリアしていますか?
- 土地の形状はいかがですか、近隣との関係は?
- 上下水道や電気、ガスなどの公共設備は整っていますか?
- 日当たりや風の向きは、水はけはいいですか、埋め立て地ではないですか、地盤の質はどうですか?交通機関、医療機関、教育機関、スーパーなどの周辺環境は整っていますか?
※特に環境は、季節・天候・時間によって同じ土地でもイメージがまるで違うことが多々あります。 それ故、何度も足を運ぶことが大切です。
土地探しの必須条件
土地を探しているお客様より、以下のような不満をお聞きすることがあります。
- 情報誌やインターネットでチェックしていても、なかなか良い情報がない
- 不動産会社が出している情報はあまり良いものがない
- 周辺環境の情報は良いことばかり聞かされるが、本当だろうか
- 良い情報だと思って、問合せをすると既に予約が入っている事が多い
このような場合の対処方法
- 不動産業者から直接情報収集する良い土地は情報誌に出すまでもなく売れるケースがあります
- 土地探しを依頼するとき希望の場所、面積、価格など具体的に要望を絞り込んで土地探しを依頼する
- 不動産業者選びは周辺環境については、不動産の大手業者だから安心とは限りません。
地域を良く知る地域に密着した信頼できる業者を選びましょう。
※出来れば不動産だけでなく建築の事を良く知る会社がお勧めです - 連絡は密に不動産業者との連絡を蜜にし、条件に合う情報はすぐに教えてもらう
土地の法的規則
その土地に家を建てるには、いくつかの法的規制をクリアすることが必要です。
代表的なものとして以下の4つがあります。
| 地目 | 土地には用途の分類があります |
| 市街化区域・市街化調整区域 | 建てることの出来る建物の制限があります |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで、住み人・使われる用途に応じた分類があります |
| 接道義務 | 敷地と道路との関係で、道路の無いところに建物が建つことを防止されています |
これらは宅地として利用するためには最低クリアしなければならない法的規制です。
しっかりとチェックが必要です。
※出来れば事前に専門の敷地調査をお勧めします。
土地探しの方法
- 土地探しのプロ(不動産会社)に依頼する
- 建築予定の建物メーカーに依頼する
- 情報誌やインターネット、チラシをもとに自分で探す
※土地探しのプロ(不動産会社)や建物メーカーに依頼する場合には、事前に条件の絞込みが必要です。
自分で探す場合は探しながら条件を絞り込んでいくことも出来ます。
肝心なことは、どれを選択するにしても自分の眼でしっかりと「土地を選ぶこと」が大切です。
売却の流れ
- 売却相談
- 調査・査定
- 現地見学
- 不動産売買契約
- 住宅ローン
- 引渡し
売却に必要な費用
お住まいを売却される場合でも、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。
つまり、売買金額から、諸費用を差し引いた残りが手取り金額となるわけです。
売買金額-諸費用=手取り金額
諸費用の内訳
諸費用の内訳は以下のようになっています。
| 地目 | 売買価格の3% + 6万円 + 消費税となります。 |
| 印紙代 | 売買契約書に貼付けする印紙代です。 |
| 所得税/住民税 | 売却によって譲渡益が出た場合、住民税、所得税がかかります。 (ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります。) |
| ローン諸費用 | ローン諸費用ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士への報酬、ローン事務手数料などです。 |
| その他 | その他引越し費用などです。 測量が必要な場合、その費用。 |
譲渡益への税金
お住まいを売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。
ただしご自宅(居住用の資産)をご売却の際は、3,000万円までの特別控除が利用できたり、
所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。
国税庁
国税庁・税金電話相談のサイト
(A)売却物件をプロが調査
お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断してもらうのが査定です。査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきます。
(B)無料査定
ご売却物件を無料で価格査定いたします。また、「とりあえずどのぐらいで売却できるのかを知りたい」「将来の買替のために現在の資産価値を把握しておきたい」という方にも、コンサルティング業務を行っています。
(C)査定価格と売り出し価格
査定では、一般的に3か月程度以内に売却できると予想される価格が提示されます。
その価格を基本に、実際の売り出し価格を決めるわけです。
(A)媒介契約の種類
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入(B)媒介契約制度の違い
購入に必要な資金
| 複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した相手との取引 | 指定流通機構への登録義務 | 業務処理報告義務 | |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |
折り込みチラシ、不動産合同チラシ、単独チラシ、手撒きチラシ(ポスティング)などを、御売却物件の地域・種類に応じて、より多くの広告媒体により、最適な広告活動を選定いたします。もちろんご近所に知られたくない、内々で売却して欲しいなど、ご希望に応じて、チラシ、広告を一切いない活動も可能です。
(A)契約に至るまで
ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を売主様と調整します。そして条件が整ったら、不動産売買契約を締結します。
(B)不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
(C)契約時に用意するもの
お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
ご本人
権利証(買主に提示します)
実印
管理規約書 (マンションなどの団地内の取り決め)
建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
固定資産税納付書
印紙代(売買金額によって異なります)
仲介手数料の半額(別途消費税および地方消費税が必要です)
運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
代理人が立ち会う場合
※代理人によって契約を締結することもできます。
委任状(本人の自署と実印を押印したもの)
本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
代理人の実印
代理人の運転免許証など(代理人ご本人と確認できるもの)
(A)その前に引越しを
一般的に残代金の受領と物件の引渡しは同時に行なわれます。したがって、通常は引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。 引越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行ないます。また、マンションなどの場合、使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておきましょう。
(B)ローンが残っているときは
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。
抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。通常は仲介業者の担当者がお客様のご都合に合わせて調整を行ないます。
(C)残代金の受領・物件引渡しの流れ
- 登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。 - 残代金の受領
残代金を受け取って、領収書を発行します。 - 固定資産税などの精算
引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。 - 関係書類の引渡し
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡します。 - カギの引渡し
お住まいのカギを引渡します。 - 諸費用の支払い
仲介手数料、司法書士費用などの諸費用を支払います。
(D)残代金の受領時に用意するもの
- 権利証(登記済証)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 固定資産税納付書
- ガス、水道他精算領収書
- 管理規約、パンフレット、建築確認書など
- 仲介手数料の残額(別途消費税が必要です)
- 登記費用(抵当権抹消登記・住所変更登記・売渡証書作成等)
- 売却物件のカギ
- ※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、上記以外にも書類が必要になります。
購入の流れ
- 売却相談
- 調査・査定
- 現地見学
- 不動産売買契約
- 住宅ローン
- 支払い・引渡し
- 引っ越し・入居
購入に必要な資金
お住まいのご購入には、物件の価格に加えて税金などさまざまな費用がかかります。 それら諸費用の合計は、売買価格の6〜8%が目安です。したがって、2,000万円の物件を購入する場合、必要な資金は2,120~2,160万円程度となるわけです。 ただし、この諸費用は物件により異なり、住宅ローンの金額によっても変わります。
諸費用の内訳
諸費用は、売買契約から引渡しまでの流れのなかで、その都度支払う費用です。 諸費用の内訳は以下のようになっています。
| 印紙代 | 売買契約書やローン契約書に貼付する印紙代です。 |
| ローン諸費用 | ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士への報酬、ローン事務手数料などです。 |
| 保険料 | 火災保険料などです。 |
| 登録免許税 | 登記に伴う税金です。不動産購入時(所有権移転登記)には固定資産税評価額の1%、ローンを組んだ時(抵当権設定登記)には借入金額の0.4%がそれぞれ必要となります。(軽減有り) |
| 登記手数料 | 登記手続きの際の司法書士への報酬です。 |
| 固定資産税(日割りで精算) | 固定資産税評価額の1.4%が1年分となります。 |
| 都市計画税 | 固定資産税評価額の0.3%です。 |
| 仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円+消費税となります。 |
| 不動産取得税 | 不動産取得税 住宅の場合、固定資産税評価額の3%です。(軽減有り) |
| その他 | 引っ越し費用などです。 |
購入可能価格の割り出し
いくらの物件が購入できるかを割り出すには、まず、月々およびボーナス時に返済できる金額から、 住宅ローンの借入金額を算出します。
月々の返済金額には、毎月の積み立て貯金額、賃貸住宅にお住まいなら現在の家賃などが目安となります。
住宅ローンの借入金額に自己資金を加えた金額が、物件の売買価格と諸費用の合計となります。
住宅ローン借入金額 + 自己資金 = 物件価格 + 諸費用 したがって、住宅ローン借入金額と自己資金の合計から諸費用を差し引いた金額が、購入可能な物件の価格です。
他の特例を受ける場合、住宅ローン控除が適用されない場合があります。
国土交通省(外部リンク)
(A)情報収集の手段
所在地や沿線・駅、間取り、価格などのすべての面で満足できる物件は、すぐには見つからないのが普通。
お住まい探しにあたっては、できるだけ多くの情報を集めることが重要です。新聞の不動産広告や折り込みチラシ、住宅情報誌、そしてこのホームページをはじめとするインターネット情報も、上手に活用しましょう。
また、地域に精通した仲介業者は、広告に掲載されている以外の最新物件等の情報も多く集まります。
(B)希望条件の整理
ただし、情報を集めることに熱中しすぎると、優良物件にめぐりあっても「もっといい物件があるはずだ」と、せっかくのチャンスを逃してしまいかねません。そうした事態を防ぐには、あなたのご希望条件に優先順位をつけておくことをおすすめします。
条件例
地域学区・予算・間取・最寄り駅、立地・環境・築年数・土地の広さ・ガレージ等
(C)仲介業者を選ぶには
「情報」は、物件についてだけとは限りません。とくにお住まいの購入は、高額な取引であり、専門知識も多く要求されますから、間違いのないように売買されなければなりません。信頼できる仲介業者を選ぶためには、以下のポイントを確認します。
宅地建物取引業免許
不動産売買の仲介業には、宅地建物取引業の免許が必要です。
また事務所には、免許証番号や有効期限を記載した「宅建業者票」の表示が義務づけられています。
免許証番号 国土交通大臣免許*A (8)*B 第777号
免許有効期間
平成○年○月○日から
平成○年○月○日まで
商号または名称 ○×不動産販売株式会社
代表者氏名 ×川△男
この事務所に置かれている
専任の取引主任者の氏名 ×山○夫*C
主たる事務所所在地 東京都○○区××1-2-3
——————————————————————————–
A:国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類がありますが、両者に優劣はありません。
B:免許の更新回数を示します。更新は5年に1回(平成7年度までは3年に1回)です。
C:事務所専任の宅地建物取引業者の氏名です。
業者団体への加盟状況
不動産業界にはいくつかの業者団体があります。各団体への加盟にあたっては、一定の基準で資格審査が行われているほか、日常業務に関しても一定の規則が設けられていますから、加盟しているかどうかも業者選びのポイントです。
【主な業者団体】
(社) 全国宅地建物取引業協会連合会
(社) 不動産流通経営協会
(社) 不動産協会
(社) 住宅産業開発協会
(社) 都市開発協会
(社) 全日本不動産協会
(社) 日本ハウスビルダー協会
(社) 日本高層住宅協会
(社) 日本住宅宅地経営協会 など
沿革・業績・店舗状況
業者免許が国土交通大臣免許の場合は国土交通省不動産課で、都道府県知事免許の場合は各都道府県の宅地建物取引業の担当局部で、それぞれ業者名簿を閲覧することができます。名簿には、代表者の経歴、事業の沿革、過去3年間の営業実績、業者団体への加盟状況、過去に業務停止処分を受けたかどうかなどが記載されています。
(A)現地見学
収集した情報を検討して、気になる物件があったら積極的に現地見学に行きましょう。
物件情報だけではわからない建物の具体的な状態や、周辺のさまざまな環境を知るには、現地を見学するのが一番です。
(B)物件のチェックポイント
現地で物件をご覧になるときは、まず第一に、チラシや広告などの情報通りかどうかということを確認しましょう。
さらに汚れなどの状態や、日当たり、風通しなど図面ではわからないことをよく確認します。
また、家族それぞれの立場からチェックすることも重要です。
【物件の主なチェックポイント】
- 敷地状況
- 内装・外装の材質、汚れ、ひびなどの状態
- 部屋数、間取りごとの使いやすさ
- 各部屋の向き、日当たり、風通し
- 車庫・駐車場、駐輪場
- 冷暖房設備設置状況
- 増改築・リフォームの必要性
- 収納スペースの状況 など
(C)周辺環境のチェックポイント
【周辺環境の主なチェックポイント】
- 交通機関の状況(駅までの所要時間、始発・最終時間、混雑状況など)
- 周辺道路の状況(交通量、混雑状況など)
- 教育施設(学校、学区など)
- 公共施設(病院・公園・図書館など)
- その他の周辺施設(商店街、スーパー、コンビニ、飲食店など)
- その他の環境(騒音など)
(D)オープンハウス情報
オープンハウスでは、実際に売り出し中のお住まいの内部を、ご自由にご覧いただけます。
開催日には、お好きな時に予約なしで、お気軽にお越しください。
(A)購入申し込みから契約まで
ご購入希望の物件が決まったら、仲介業者に購入を申し込みます。
その際、購入申込書を提出します。
これを受けて仲介業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。
そして条件が整ったら、重要事項説明を経て、不動産売買契約を結びます。
(B)重要事項説明
重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。
これは宅地建物取引主任者の資格をもつ仲介業者が、「重要事項説明書」によって説明を行います。
重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の 規定などが記載されています。不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
(C)不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。
売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを 明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って 契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
(D)契約時に用意するもの
お住まいのご購入に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
・印鑑(ローンご利用の場合は実印となります)
・手付金(現金か預金小切手かを事前に確認しておきます)
・印紙代(売買金額によって異なります)
・仲介手数料の半額(別途消費税が必要です)
※ローンご利用の場合は、ローン申し込み用書類も必要です。
(A)公的融資と民間融資
住宅ローンは、大きく分けて「公的融資」と「民間融資」の2つに分けられます。どちらを利用するかは、利用者の資格条件や取得する物件によって決まります。
公的融資
| 住宅金融公庫融資 | 購入する住宅が所在する都道府県内の「住宅金融公庫業務取扱店」と表示された金融機関で手続きをします。固定金利の割に金利が低い、抵当権設定時の登録免許税が免除になるなど利点が多いのですが、金利に保険料が含まれない、つなぎ融資が必要な場合があるなど不利な点もあります。 |
| 年金住宅融資 | 厚生年金保険、国民年金の加入者を対象とした融資です。 |
| 財形住宅融資 | 勤務先で財形貯蓄をしている人を対象とした住宅ローンです。 |
民間融資
銀行、信用金庫、生命保険会社、住宅金融専門会社、信販会社などの民間金融機関が、それぞれの規定に基づいて 行う住宅ローンです。したがって、金利や融資限度額、返済方法なども各金融機関によって異なりますが、融資条件は 一般的に公的融資よりもゆるやかです。
(B)ローンのお申し込み
住宅ローンのお申し込みには、以下のものが必要です。
- 住民税決定通知書 (公的所得証明)
- 原産徴収票
- 実印と印鑑証明
- 住民票(家族全員のもの)
- 健康保険証写し
- 重要事項説明書
- 不動産売買契約書の写し
- 融資の申込書類一式(融資機関ごとに異なります)
- 印紙代 など
(A)公的融資と民間融資
入居後のトラブルを未然に防ぐため、売主・買主双方で、物件の状態についての最終確認を行います。
物件最終確認のポイント
付帯設備表の内容との一致の確認
物件状況報告書の記載内容との一致の確認
(雨漏り・シロアリの害/建物構造上主要な部位の木部腐食/給排水設備などの故障)
隣地との境界の明示 電気・ガス・水道の使用方法、故障時の連絡先の引き継ぎ
(B)残代金支払い時の流れ
登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行います。
登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
残代金の支払い
手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を支払います。
固定資産税などの精算
登記費用を支払い、固定資産税などを精算します。
関係書類の受け取り
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを受け取ります。
カギの引渡し
お住まいのカギを受け取り、その確認として「不動産引渡確認証」を発行します。
諸費用の支払い
仲介手数料などの諸費用を支払います。
(C)残代金支払い時に用意するもの
残代金
仲介手数料の残額
登記費用(登録免許税および司法書士への報酬です)
固定資産税/都市計画税、管理費などの精算金
住民票
印鑑(実印)
印鑑証明書(抵当権設定時のみ必要となります)
住宅ローンの諸費用(火災保険料、保証料、銀行費用等)
(D)登記手続きとは
「登記」とは一定の事項を広く公示するために、公開された帳簿に記載することを意味します。
その目的は 取引の安全を保護することですが、不動産取引においては、登記の手続きは司法書士に依頼します。
司法書士は、必要書類を預かって登記の申請書を作成し、法務局に提出します。
登記済みの権利書などを 司法書士から受け取ったら、紛失や破損などがないよう注意して保管してください。
(登記済権利書の再発行はできません)
お引越しの準備
お引越しでは、住民票の移動届や学校への転校届をはじめ、電気・ガス・水道・電話の移転手続き、金融機関・保険会社への住所変更届、さらに荷物の整理・梱包、粗大ゴミの処分、冷蔵庫内の食品の処分、近所へのあいさつなど、やらなければならないことがあまりにも多くあります。
どこで何をしなければいかないか、誰に何をしなければいけないかなど、あらかじめ計画を立てて準備しておきましょう。
買い替えの流れ
お住まいのお買替をされる場合は、ご売却とご購入のタイミングが重要となります。
両者を同時に行えるのが理想なのですが、なかなか現実には難しいものです。
したがって、お買替の場合には「ご売却先行」と「ご購入先行」の2つのケースが考えられます。

売却が先? 購入が先?
売却を先行させるか購入を先行させるかは、市場動向に合わせるのが基本。一般的に、売却が難しいときは売却を先行させ、逆に、購入希望者の多い人気の地域に物件をお持ちの場合は購入を先行させることをおすすめします。
購入可能価格の割り出し
| メリット | 購入資金に充てられる金額が確定するので、ご購入の資金計画が立てやすくなります。 |
| デメリット | 購入したい地域の物件が少ないなどの理由で、ご希望物件がなかなか見つからないことがあります。 引渡しまでに新居が決まっていないと、その間の仮住まいを用意しなければなりません。 |
「ご購入」先行の場合
| メリット | 仮住まいなどの費用がなくなり引越しもスムーズです。 希望条件にあった物件を、じっくりと探すことができます。 |
| デメリット | 売却のめどが立たないと、つなぎローンなどの手続きや費用がかかります。 |
Mシステム

「M システム」とは、皆さまの心強いパートナーとして投資・効率活用する“資産活用システム”です 皆さまの大事な資産(土地・家・マンション・アパート等)を、ご負担をかけることなく有効に「活用し」・「残し」かつ、「資産継承」させる、安全で、魅力的なハートホームだけの資産活用システムです。
よくあるご質問
日本住宅保証検査機構(JIO)の瑕疵保証をお付けしております。
保証の内容として、主要な構造部分において欠陥が生じる事は、まず考えられない事ですが、それでも入居後10年以内に、万が一、何らかの不備で欠陥が生じた際は、保証が適用されます。
さらに平成21年10月1日よりスタートした住宅瑕疵担保履行法にも対応しております。
住宅業界では、より快適な住空間にする為に外気との断熱が研究され続け、最近の住宅では気密性が飛躍的に向上しました。しかし、家屋の呼吸である換気が上手に管理できなければ、本当に快適な生活は得られません。従いまして、24時間換気システムは高気密住宅に必要不可欠なものなのです。
換気システムの主な目的としては、
・二酸化炭素を排出して、新鮮な空気を導入する。
・部屋中の余分な水蒸気を排出する。
・臭いや埃、塵を排出する。
・揮発性有機化合物(VOC)を除去する。
などが挙げられます。
確かにそのようなお話を聞いた事はありますが、全ての人に対して当てはまるわけではないと思います。
「心呼吸の家」では、人にやさしい自然素材を多く使用していますので、アトピー性皮膚炎や喘息、シックハウス症候群を起こしにくいとは考えられます。
このような症状でお悩みの方は是非一度、完成見学会等で「心呼吸の家」を体感して、ご自身の症状を確かめてみてはいかがでしょうか?
まだまだ、土地探しにご苦労されているお客様も多いのではと感じています。
三浦建設は、住まい創りの近道を探させていただければと思い、地域の不動産グループや地元大手不動産会社などとネットワークを組んでおります。
皆様の不動産購入を、安全・安心いただき皆様の住まい創りがより良いものになるようにとお客様の立場に立って土地の情報をお知らせしております。
又、当社は地質専門会社とも提携しておりますので、ご希望の土地が見つかりました場合は、その土地付近の地質情報(太古の時代よりの地質状況)も合わせてお知らせしております。
安い土地だからとご購入されても、後の地盤補強等で高額になる場合もございますので、購入前に地質調査をしておくと安心です。
残念ながらモデルハウスは御座いません。
モデルハウスは建築費、維持費と多くの費用が掛かります。結果として、それが販売価格を高くしてしまいますので、弊社ではモデルハウスをお作りしておりません。ただ、三浦建設でお建て頂くお施主様のご好意により見学会を催しておりますので、ぜひご参加いただき、体感してください。
はい、大丈夫です。 ただ、リフォームはある意味、新築よりも経験や技術を要求されます。
三浦建設「ハートホーム」のリフォームでは、まず耐震性能を一番に重視します。次に「心呼吸の家」の快適住宅技術を駆使し、過ごしやすい住空間造りをご提案させていただきます。
三浦建設は神社や仏閣の改修もさせていただいている建築会社ですので、お客様の家を見させて頂ければ、大体どこが悪いか診断をする事ができます。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。診断だけでも構いませんよ。
お引き渡し後は定期的にメンテナンスにお伺いをしている他、何かあれば随時お伺いして素早い対応をするようにしております。どうぞお気軽にお声をおかけ下さい。
後々のアフター点検等も考えて、すぐに駆けつける事ができる距離(京都府、滋賀県、大阪府)を基本とさせて頂いておりますが、状況に応じて遠方の方にも対応しております。もしエリア的に少し遠いなと思われた場合でも、お気軽にお問い合わせ下さい。
三浦建設の「心呼吸の家」では、お引渡し間近のお住まいをお借りしての完成見学会や、柱・梁・補強金物取り付け後など構造部をご覧頂く構造見学会を、お客様のご好意により不定期開催致しております。
又、どうしても見学会に都合がつかない方や、しばらく見学会の予定が無い場合などは、個別でのご案内もさせて頂いております。お施主様への同意が必要とはなりますが、興味をお持ちの方は、是非お気軽にお申し付けください。
やはりご自身の肌で感じ取って頂くのが一番わかりやすいと思います。
是非、現場見学会に参加していただき、ご覧になってみて下さい。
ご見学頂いた皆様には共通して「過ごしやすそう」という感想を頂いておりますし、お施主様からも良かったと言ってもらっています。
確かに「心呼吸の家」は自然素材を多く使用していますので、値段も高く考えられがちですし、実際にそういったご質問をされるお客様もいらっしゃいます。
家造りというのは、一生に一度あるかないかのご決断ですので、とことん時間をかけて、建てる金額だけではなく総合的に判断して下さい。家を建てた後にかかるメンテナンスコストや、ランニングコストなども考慮しなくてはいけません。
弊社のお客様の中にも、完成見学会にお越し頂いた後、何年にも亘り他のハウスメーカーや工務店の工法などをとことんご研究され、最終的に「行きつくところは三浦建設だったね」とご契約を頂いた例もございます。
私たちは先人が育んだ知恵と技術を生かし、自然素材という健康素材に命を吹き込み、住み手とともに手を入れることで50年・100年と住み続けることの出来る長寿命住宅「心呼吸の家」を創りたいのです。
近年の新建材を使った家は 「いつでも綺麗で、手間いらず」。しかし、綺麗なのは新築時だけではないでしょうか。時間の経過とともに劣化し、早ければ25年で寿命を終える住宅につながります。 このような家を私たちは「クリーンな家」とは思いますが、健康的で味のある「ビューティフルな家」とは思いません。だから、私たち三浦建設は自然素材をつかった「心呼吸の家」をお勧めしております。
住宅の価格では「坪単価」を価格の指標として考えるケースがよく見受けられます。
しかし、坪単価はお客様目を惹き付けるキャッチフレーズにしか過ぎません。何故なら坪単価は延床面積が広くなるほど安くなりますし、各ハウスメーカーや工務店の認識並びに表現の違いによって、実際には別途工事費や諸費用がお見積書に含まれていなかったりするケースが多々あります。それ故、大雑把な目安としての意味はあるでしょうが、あまり坪単価を重視するご検討方法は正しい判断とは言えません。
確かに、「心呼吸の家」は高性能住宅であるが故、坪単価に換算すると高い金額になりがちですが、三浦建設ではお客様との打ち合わせを基に、本当に必要な金額でお見積書を提出させて頂いております。
はい。弊社内に不動産部を設けております。
お客様のご要望に沿ったお勧めの物件をご提案させていただいております。
正式名称は「次世代省エネルギー基準」と言います。快適に住む事ができる住宅性能の目安として建設省が定めた基準値です。
「熱損失係数(Q値)」「相当隙間面積(C値)」などの、クリアすべき基準値が地域別に定められています。
24時間換気システムが稼動しているので大丈夫です。
24時間換気システムによって、常に必要な空気の量が保たれ、又その空気は常に新鮮な空気ですので、快適で健康的な住空間が24時間保たれます。
24時間換気システムの作動中は窓を開けてはいけないということでもありませんので、たまには窓を開放してみるのも良い事です。ただ、24時間換気システムに頼った方が空気の入れ替えは早く出来ますよ。
*24時間換気システムの主な目的としては、
・二酸化炭素を排出して、新鮮な空気を導入する。
・部屋中の余分な水蒸気を排出する。
・臭いや埃、塵を排出する。
・揮発性有機化合物(VOC)を除去する。
などが挙げられます。
「かし」と読みますが、要は欠陥と同じ意味合いです。新築住宅の場合では、引き渡した住宅の品質や性能が、当初お約束したものと異なる場合を言います。例えば、設計図書に従った施工が行われていなかったり、最低限有する性能が確保されていない場合には瑕疵に相当します。
近年の地震の多発から、耐震性能は特に心配な事だと思います。
三浦建設の「心呼吸の家」では、入念な地盤調査と地震に強い補強金物による耐震性に優れた工法を採用しています。それ故、地震だけでなく台風等の強風にもしっかりと耐える、耐震性、遮音性、ともに優れた住まいです。
三浦建設の「心呼吸の家」は24時間計画換気しています。その吸気口にはフィルターがついています。花粉の侵入も防ぐので花粉症にも有効なようですが、個人差があると思いますので判断は難しいところです。
花粉症でお悩みの方は是非一度当社の現場見学会や施工済みの建物をご見学いただき体感して、ご自身の症状を確かめてみてはいかがでしょう?
最近はIHクッキングヒーターやエコ給湯器、更には防犯関係のセキュリティシステムなどの設備機器も進歩し、種類も豊富になってきました。
三浦建設では、お客様のご要望をお聞きした後、過去の施工事例やカタログなどからご提案させて頂いておりますが、各社ショールームなどへもご案内させて頂き、実際に実物を見て頂く事も致しております。